2023年度、最後のゼミが3/21(木)に行われました。
修了生のお二人に、1年間の修士研究/修士設計を振り返っていただきました。
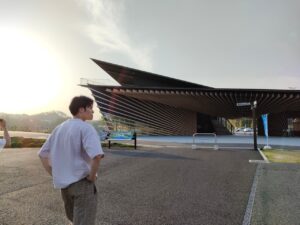
鶴岡 稜悟 修士設計
「裏水路地 四ツ谷用水本流を対象とした八幡地区における線状環境空間の提案」

島守 彩寧 修士設計
「過去のイマージュを繋ぎ合わせて」
<トークテーマ>
・対象となるテーマや地域の決め方/決まり方
・一番大変だったことは何か?
・取り組んできて、到達したこととは何か?
<対象となるテーマや地域の決め方/決まり方>
鶴岡:決め方は最初は好きなことや、興味があることを箇条書きで上げていって、そこから関連した先行研究や書籍を読みながら、自分がやろうとしていることが研究に値するか、社会的な意義があるか、考えていった。1年間やり続けられそうなことを決められた。
興味があるものや文字をばーっと挙げていった、それを図式化した資料をつくった。はじめは、(島守と)二人で修士設計をやろうと考えていた。興味も似ていたし。よくよく考えたら考え方にも違いがあったし。別々に考えてみることも検討した。
窪田:違う意見の人とも一緒に空間を形成することになるのでは?グループ設計が多かったので、一人で深めていって出し切るという卒業設計と、後者を修士設計でやってみるという中で。複数人でやる意義は今後絶対必要になってくると思うので、今後も身につけたいところ。
島守:二人でやろうという話があれば、根底に(修士設計の進め方や評価に、これまでとは)違うところがあるだろうなと思っていた。成果物も全然違うが、共同設計をやったらやったで面白かったろうけれども。もし二人でやった場合に、どういう成果物を求められるか、評価も厳しくなってしまいそうだし。窪田研に入ってすぐだったし。今後の後輩も(そうした状況を考える事は)ありえると思う。社会でやっていくうえでは、お互いに高めあったりもできるかも。修士設計とか卒業設計でなくてもコンペもあるし。
鶴岡:「研究に値するか、社会的な意義があるか」とは、第三者的というよりは、今やっている身近なテーマが自分自身が社会に出て生きるかどうか、自分だったら地域性とか都市の在り方。自分が今研究していることが社会において役に立つかを考えていた。こういう知見があって、書籍化されたり論文化されたりした堅苦しいことよりも、自分自身で考えることにつながっているかどうか。社会的な意義とは何か、というよりは、自分自身が社会に出たときに、テーマにどういう意義があるかどうか。僕のテーマが地域や地区を深掘りしていくテーマだったので、どんどん深めていったときに、自分がやりたいテーマや培った考えが、他の地域で考えたときに、役に立つのではないか?
窪田:図面化も良いが、論文化するということで、展開することもできる。
植田:修士設計ではプロジェクトを通して生きていくのではないか。
島守:記憶についてはやりたいと思っていたのは、普段考え事をしていて記憶を参照していた中で、色々と繋いで考えているということがあったから。そういう中で、ベルクソンを知人から紹介されて、なかなか本を正しく読むことができなかったりして、(中間発表などで)モビリティやアーケードに逸れたりして、逃げではなくても道がわかりやすかったので、そちらを考えつつ、記憶の話を手離さないようにしていた。本も再読したりして。
自宅に場所を選定する前は、アーケードに設定することで色んな人に還元したいと思っていたが、社会的意義と自分の記憶を生かすというのが合わないように思った。自分の記憶と全然関係無い人にそれを還元することは、適切ではないと考えた。
自分自身に還元した方が良いと思うようになり、自分に対して深掘りしようとするのであれば、24年間暮らしてきた自宅が良いと思った。
はじめは、他人とか社会に還元について、社会の人が何を享受できるかということを考えていた。そこから考え方を変え、自分の中で起こったことを自分の表現でやっていくことにした。当時は、還元とは何かがわからなかった。今では、「自分の中の個人的な記憶だったり、あまりきれいとは言えない記憶だったり、そうしたものこそ自分にとって重要な判断材料や、自分の軸を決めている」ということを社会に伝えることが、私にとっての還元なのだと思っている。
植田:アーケードか自宅かどっちかで12月後半ぐらいまで悩んでいた印象。自分の記憶を扱うという話になったときに、アーケードでまちの人の記憶に触れる可能性もあるかと思っていた。島守さんが自分の記憶、内省的な方向に向かっていったので、どっちの方が面白さが出るかと思っていた。
ベルクソンに本を読んで建築と接点がでないかとのことだったが、インプットしたものを建築に変換して考える姿勢なのか?
島守:そういうわけではなかった。修士設計をやるにあたって無理くり接点を持たせようと思った。
植田:参照点をもっておくことが重要だということでしょうか。

写真1. 研究室旅行、南三陸にて隈研吾設計の大橋
<1番大変だったことは何か?>
島守:二つあって、本を読むというところも正しく読めているかわからなかった。抜き出して考えたり、ネットを読んだり、他の本を読んでみたり。いまだにわかっていない部分もあって、設計につなげた部分は自分なりに理解したつもりではある。もう一つは、夏から12月まで、社会的意義というか、(窪田先生が言っていた)「結果的につくってよかったと思える、良い記憶をつくれる場所」、というのがよくわからなかった。社会的意義を念頭にするとやりたいことから離れている感じはあった。そこら辺を決めかねていた、12月頃までくすぶっていた。
窪田:うまく伝わっていなかったかもしれない。私は、「個人をどう大切にできるか」ということを見せられれば非常に意義があると思っていた。
島守:成果物として表現するのが難しいと思っていた。
植田:社会的意義が、公共的な建築や空間をつくるとなると、わかりやすい。都市計画とか都市デザインというよりかは、個人の一建築や私有的なことを考えていた印象だが、(島守と鶴岡が)M1まで旧石田研で建築を学んできたので、その考えの違いが過渡期だったからこそあった気がする。その考えの違いに触れたことで(教員と学生の考えをもっと共有)できたことかもしれない。
島守:もう少し過渡期が続くと思うので、来年再来年の学生もそんな壁にぶつかるのではないかと思う。お互い、学生側も先生側も、わかったうえでテーマを決めていくということが大事。
鶴岡:水路を扱ったのが一番大変。環境は考えてきたつもりだったが、流動的なものと、そこにあり続けるものと、まちとか歴史とか文化とか。色んな考えがどんどん巻き起こってきたときに、流動的で物体がある水路をどう扱うか、が建築的にも土木的にも、人と水の関わり方など、考えることがいっぱいあるなということが大変だった。
構造や土木は説得力をもたせるために、調べていった。この時期にはこれぐらいの雨量があるから、これぐらいの傾きにすれば溢れないようにできるなとか。水の染み方や涵養の仕方。今まで(の設計課題など)は、ここに池を作ります、というゲーム感覚のようなものだったが。実際にどう作るかとか、どのくらいの水量が出てくるか、とか考えたのが初めて。
窪田:ゲーム感覚から抜け出させた契機は?
鶴岡:最終的に成果物として出すと考えたのは、説得力を持たせるためには、どんどん根拠を持たせないといけない。そう考えたことがきっかけだった。個人の設計の仕方にもよるが、建物をつくるときにあやふやなところを考えることを重要とすることもある。思い切りも大事だが、実現可能性と理想性のバランスをとるなど。設計をするときに考えているのは、自分の中で二人いて、やりたいことをぽんぽんと、構造や重力とか考えないで作り出していって、実際に建てるときに、課題が出てきて、それを解くというやり方。理想と現実を考えたときのバランス(がとれると思う)。
窪田:条件をどう設定するか、を考えるのがうまい。物理的なものは制限条件になっても社会的には変えられる。そこらへんの判断が鶴岡君はうまいと思う。
鶴岡:上手ではない、ですよ。でもずっと考えてはいる。

写真2. 研究室旅行、花露辺にてまち歩き
<取り組んできて、到達したこととは何か?>
鶴岡:地域の理解度は一定のラインを超えたのではないか。それが終わりではなくて、そこから考えていくのが結構大変で、難しいことでもあり、逆にいえば楽しいこと。今後、それを考えていきたい。あるものを対象としたときの、捉え方が深まった感じ。100%理解ということではないが、設計するにあたって、建物をちゃんとつくるという基礎となるラインを、ようやく身につけられたというイメージ。何かしらの敷地とか地域を対象にしたときに、ある一定のラインを超えると楽しくなってくる。最初のころは情報収集とか単純にしてきたが、人と接する機会があって一定のラインを超えたときに、楽しくなる。
植田:鶴岡君は現地で発表したりした?
鶴岡:大きなものはないが、道端であった地域住民に口頭で、四谷用水の横で「こんなふうな設計をしました」ということは伝えた。
植田:現地発表とかすると、また色んなことが起こってくるのでは?現場の方から言われることにも全然違う意味がある。
鶴岡:地域の人の思いや関わり方も変わってくるので、思い入れのない人もいるし、ある人もいらっしゃる。同じ説明をしても。
窪田:地域の人に伝わるように、ここで何を学んで何を考えたか、作って伝えてほしい。
島守:自分の内的なこととしては、やりたいことをやり切れたという感じはある。評価は気にしなかったけれど、評価された。自分の記憶を分析する中で、自分にとって今、最近ではやるような行動の理由や軸になっていることが、何からきているのか、昔の記憶から得られた学びから、やっていることがわかるようになって、自分の行動の特性がわかるようになって。論文の最後にも書いたが、「普段着目しがちなのはSNSに載せるのはきれいなものや美味しいもので写真としては残るけれど、今の自分に働きかけてくるものは他の人には語らない部分であり、自我や性格が(そうしたものによって)出来上がっている」ということに気付かされた。評価を気にしていたっこともあった。同期や後輩にも見られていて、票も入れられちゃうんだ、と。自分が好きなことをやってゼロというのも悲しいし。でも、自由にやった方がすっきりする。
卒業設計だったら吹っ切れることは無理だっただろう。修士設計だったから(就活に活かされるような評価軸をもつことなど、)しなくちゃいけないこともないし、評価にとらわれる必要がないし。ただただ自分がやりたいことをやれたらよかった。いつも中途半端に評価を得ようというところがあったので、鶴岡君が丁寧な設計をしているのを横で見て、それと同じようにやっても二番手になるだけ、違う土俵でやった方が良いと思っていた。評価を気にしない、違う路線で行こうと思った。それはまた、評価を狙ったということでもあるかもしれないが。重要なことは、自分の路線をいったということ。
以上

写真3. 研究室旅行、花露辺での集合写真

写真4. 修了おめでとうございます…!
